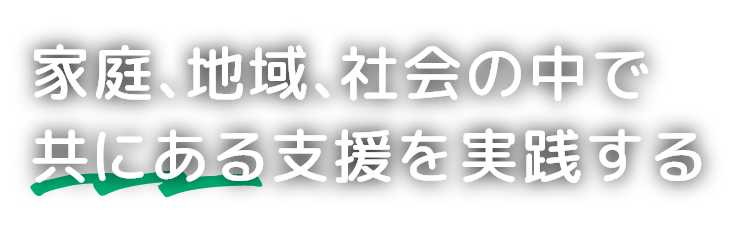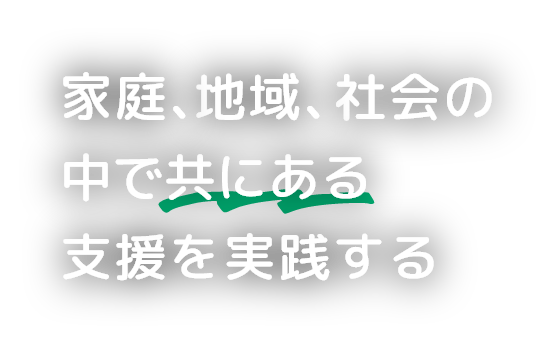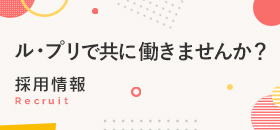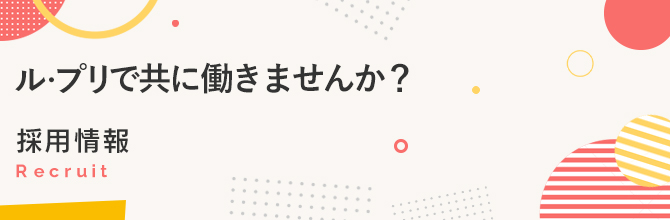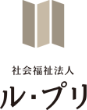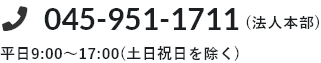福祉課題の解決に取り組む社会福祉法人ル・プリ
多くの要素が折り重なった福祉課題の解決に向けて、布地に表れる襞のように柔らかく、
折り目正しい姿勢で、関わる人すべての「ウェルビーイング(well-being)」に取り組みます。
法人事務局のお知らせ
-
2025.07.01
お知らせ
男性労働者の育児休業等の取得状況(2024事業年度)
- 法人事務局
-
2025.07.01
お知らせ
女性の活躍に関する情報公表(2024事業年度)
- 法人事務局
-
2025.07.01
お知らせ
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表(2024年度)
- 法人事務局
-
2025.04.01
お知らせ
居宅介護支援事業所 開設のお知らせ
- ケアリンク中野 (事業所番号:1473501870)
-
2024.07.01
お知らせ
(2023事業年度)男性労働者の育児休業取得率の公表について
- 法人事務局
-
2024.07.01
お知らせ
(2023年事業年度)女性の活躍に関する情報について
- 法人事務局
-
2024.07.01
お知らせ
(2023事業年度)労働施策総合推進法に基づく中途採用率について
- 法人事務局
-
2023.08.11
お知らせ
(2022事業年度)男性労働者の育児休業等の取得状況について
- 法人事務局
-
2022.11.17
お知らせ
労働施策総合推進法に基づく中途採用率について
- 全施設対象
施設別のお知らせはこちら
高齢福祉施設
児童福祉施設
保育施設
法人事務局
About us
私たちについて
《ル・プリ》に込めた想い
《ル・プリ》LE PLIとは、フランス語で「襞(ひだ)」のこと。しわとしわが折りたたまれ
表と裏が重なり合った襞のように、家庭、地域、社会の中で重なり合う、さまざまな福祉課題を
解決していくことが私たちの使命です。
私たちの名前である《ル・プリ》には、もうひとつの込められた意味があります。
襞を持つ布地のように、あるときは相手との関係を優しくくるみ、あるときは相手との関係に
折り目をつけて、関わり合う人すべての「ウェルビーイング(well-being)」を実践することです。
私たち社会福祉法人ル・プリは、こうした考え方と感じ方に則って、
支援の形を作っていきたいと考えています。
Recruit
採用情報
半歩先の「未来」を一緒に
ル・プリの職場には、あなたを必要とする人とのかけがえのない出会いが待っています。
他者を支援することで自らも生きる手応えを得る。そんな未来を一緒に目指しませんか?
Works
ル・プリの仕事内容
「ウェルビーイング」
を実践する
ル・プリの活動分野はぜんぶで4つ。支援の相手や仕事の内容はそれぞれ異なりますが、
「ウェルビーイング(well-being)」の実践を目指す姿勢は、すべての分野に共通です。
Institution
施設紹介
横浜の福祉を支える
「地元密着型」施設
ル・プリが運営する各施設は、それぞれ横浜市の地域密着型。
保育から障碍福祉にいたるまで、支援が必要なご本人はもちろん、地域のニーズにもしっかり応えます。
施設情報検索

Corporation
法人情報
多層的な福祉で
ウェル・ビーイング
を目指す
ル・プリが目指しているのは、
事業を通して関わるすべての人の「ウェル・ビーイング」。
その実現に向けた取り組みや法人の強みを紹介します。